伝統的な農家の間取りにおいて広く用いられた四間取は、4室程度の部屋を廊下で___形式である。
リビングアクセス型は、各戸の表情を積極的に表に出すことを意図して、個室を共用廊下側に設けた住戸タイプである。
各住戸において、日照・採光・通風・眺望等の条件がほぼ同一で、階段室形式に比べてプライバシーを確保しやすい片廊下形式を採用した。
階段室型の集合住宅において、高齢者向けに改修するために、玄関の位置を変更し、共用廊下を増築してそこに着床するエレベーターを設置した。
「ゲタばきアパート」は、低層部分に店舗等を設け、その上階に住戸を重ねた集合住宅で、市街地に多い。
スケルトン・インフィル住宅の計画において、将来の住戸規模を変更できるように、戸境壁には乾式工法を採用した。
住戸における「L(居間)+D(食事室)+K(台所)型」の平面計画は、各室をそれぞれの用途に応じて充実させることができるが、不十分な規模で形式的に分離させることは、かえって生活を窮屈にすることもある。
LD(リビングダイニング)は、日本の従来の茶の間に類するもので、空間を有効利用して、リビングとダイニングの機能を確保できる。
近隣コミュニティの育成を促すために、家族の使用頻度が高い居間や食事室を共用廊下・階段等に向けて配置した。
居住者の共有意識が生まれるようにするために、廊下・階段・エレベーター等の住戸へのアクセス路を日常的に共用する住戸群をグルーピングして配置した。
住戸の平面計画におけるDK型は、小規模住戸向きであり、食事と就寝の場は分離するが、団らんと就寝の場は重なる傾向がある。
デュアルリビングは、廊下に面してリビングルームをもつ二棟の片廊下型住棟を向かい合わせに配置し、部分的にエレベーターホール等で連結した住棟形式をいう。
中廊下型住宅とは、中廊下を設けることにより、動線を明快にし、各室のプライバシーを____近代の住宅のスタイルである。
中高層の集合住宅におけるツインコリドール型は、一般に、中廊下型に比べて、採光、換気等の居住性は改善されるが、通路の面積は大きくなる。
階段室型において、住戸へのアクセスが単調にならないように、階段をライトコートと組み合わせて計画した。
集合住宅の住棟計画において、各住戸の日照・採光・通風・眺望等の条件がほぼ同一であり、階段室型に比べてプライバシーを確保しやすいツインコリドール型を採用した。
スキップ片廊下型において、住戸専用率を高くするためにメゾネット形式の住戸とし、共用階段から非廊下階へのアクセスをなくした。
スキップフロア型は、廊下階以外の階を2面開口として採光や通風を確保する等により住戸の居住性を高めることができる。
ボイド型において、エレベーターホールや共用階段の近くにコミュニティの形成を目的として共用のテラスを計画した。
ホール型は、片廊下型に比べて、各住戸の日照・採光・通風・眺望等の条件を均一にしやすく、プライバシーの確保も容易である。
囲み型による配置は、住棟の方位を振ったり、住棟を曲げたり、ずらしたりして、まとまりのある屋外空間を形成する手法である。
分譲集合住宅の共用部分において、形状の著しい変更を伴わない大規模修繕工事について、区分所有者数及び議決権の各過半数の決議を経て行うこととした。
中廊下型において、各階のエレベーターホールに隣接して共用のテラスを設け、日照に配慮して廊下を(東西・南北)軸とする配置計画とした。
基準階の平面計画において、(東西面・南北面)にコアを配置して窓を減らすことで、熱負荷の影響を軽減した。
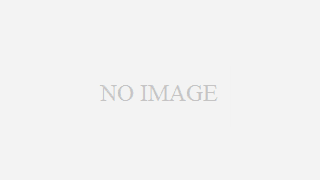 基礎知識
基礎知識 