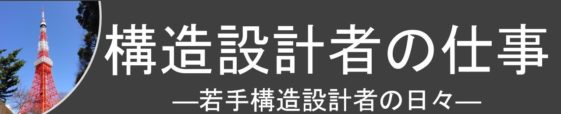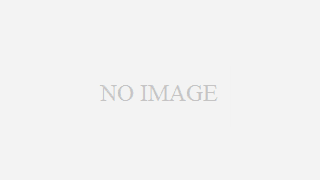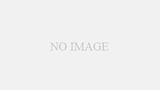はじめに
構造計算書に欠かせない「荷重」の考え方、あなたは自信がありますか?建物の安全性を左右するこの重要な知識を、初めて挑戦する新人設計者が、頼れる上司から学びます。一貫計算ソフトの使い方や実務での注意点も交えて、初心者でもスムーズに理解できる内容にまとめました。この記事を読んで、構造設計の基礎をしっかり身につけましょう!
荷重組合せについて
荷重って?

アキさん、構造計算書の『荷重』についてご確認していただきたいです。もれがないか確認したいです…

そうね、まず『荷重』って一言で言っても、いろいろ種類があるの。基本的には建物が安全に立つために、どんな力がかかるかを考えるのがポイントよ。

いろいろ種類って、例えば?

代表的なものは5つ。『固定荷重(G)』『積載荷重(P)』『積雪荷重(S)』『風荷重(W)』『地震力(K)』ね。その他としてはクレーン荷重、土圧、水圧などがあるよ。まずは代表5つについてそれぞれ簡単に説明するわ。
1. 固定荷重(G)

固定荷重は、建物そのものの重さ。たとえば、梁や柱、床、壁などの構造部材の重さや、仕上げ材、固定された設備なんかが含まれるの。

ああ、つまり建物の『自重』ってことですね!

その通り。そのため、材料の密度や体積を基に計算するのが一般的ね。
意匠図の仕上げや設備機器の重量も確認する必要があるから意匠・設備設計者に確認が必要よ。
2. 積載荷重(P)

次に積載荷重。これは人や家具、車両みたいに、建物の上に載るものの重さね。ただし、動く可能性があるものだから固定荷重とは区別されるの。

なるほど。例えば、オフィスの床に置かれる机や椅子なんかがこれに入るんですね?

その通り。住宅なら人が歩く負荷、工場なら重機の重さなんかも含まれるわね。計算に使う値は『建築基準法施行令』の別表に載っているから確認して。
3. 積雪荷重(S)

積雪荷重は、屋根や構造物に積もる雪の重さを考慮したものよ。地域や気候条件によって異なるから、設計時にはその地域の積雪量データを参考にする必要があるわ。

雪の重さも考慮しないといけないんですね。地域によって違うんですか?

そうよ。多雪地域では特に注意が必要ね。建築基準法や各自治体の基準を確認して、適切な値を設定することが大切よ。
4. 風荷重(W)

風荷重は、風が建物に与える力のこと。建物の高さや形状、立地条件によって影響が変わるの。

高い建物だと風の影響が大きそうですね。

その通り。風荷重の計算には、建築基準法や『建築物荷重指針(日本建築学会)』を参考にして、適切な風圧力を設定する必要があるわ。

風は局所的に発生しそうですが、何か配慮する必要はありますか。

鋭いわね。風の場合は、架構用(建物全体)と外装材用(局所的)があるため、注意が必要よ。
5. 地震力(K)

最後に地震力。これは地震の揺れによって建物にかかる力のこと。日本は地震が多いから、特に重要な荷重ね。

地震の力も考慮するんですね。

そうよ。地震力の算定には、『建築基準法』や『構造計算指針(日本建築学会)』を参考にして、適切な設計用地震力を設定することが求められるわ。

ちなみに外装材や二次部材(スラブや小梁=端部がピン接合)は地震力を負担しないから地震力の検討は不要よ。
荷重の組み合わせ

これらの荷重をどうやって組み合わせて設計するんですか?

良い質問ね。設計では、これらの荷重を組み合わせて、建物がどのような状況でも安全であることを確認するの。一般的には、長期荷重と短期荷重の組み合わせを考慮するわ。

長期荷重と短期荷重?

ええ、例えば以下のような組み合わせがあるの。
長期荷重
- 一般地域: G + P
- 多雪地域: G + P + 0.7S
短期荷重
- 積雪時(全地域 ): G + P + S
- 暴風時(一般地域): G + P + W
- 暴風時(多雪地域): G + P + W + 0.35S
- 地震時(一般地域): G + P + K
- 地震時(多雪地域): G + P + K + 0.35S

地域によって組み合わせが変わるんですね。

その通り。地域の条件を最初に確認することが重要よ。建築基準法や各自治体の基準をチェックして、適切な荷重を設定することが大切ね。

また上記で示した荷重組合せは架構用です。支配面積が小さい、二次部材では積雪荷重も1.0倍で設計します。
【実務でのアドバイス】

具体的に実務で気をつけるポイントって何かありますか?

そうね、いくつか挙げるわ。
- 基準書と条例の確認
- ポイント: 設計用荷重は建築基準法だけでなく、自治体ごとの条例にも影響される場合があるから、事前に確認しておくこと。
- 用途と荷重の関連性
- 例: 住宅、オフィス、工場など、用途によって積載荷重や特別な荷重が異なる。
- アクション: 設計条件に合った値を設定する。
- 一貫計算ソフトの設定
- 注意点: デフォルトの設定が地域や設計条件に合わないことがあるので、必ず確認・修正する。
- 結果の妥当性確認
- 方法: 荷重や組み合わせの計算結果が、物理的にあり得る値かをチェックする。
- 他部署との連携
- 理由: 荷重の設定には意匠設計や設備設計との調整も必要になることが多い。
- 例: 設備の配置による荷重の増減。
最後に

荷重の種類とその組み合わせ方がよくわかりました。地域の条件や建物の用途に応じて、適切な荷重を設定することが大切なんですね。

その通りよ。荷重を適切に設定するのは構造設計の基本中の基本。間違えると、過剰設計になったり、逆に安全性が足りなくなったりするから注意が必要ね。

一貫計算ソフトを使うとはいえ、どういう計算が行われているのかを理解しておかないとダメですね。

その意識は大事ね。荷重の設定ミスがあると、計算結果全体に影響が出るし、場合によっては致命的な設計ミスにもつながるわ。

なんだか、荷重の設定が建物の安全性を左右する重要な作業だって実感してきました。

その意識を持てるのは素晴らしいことよ、タケル。最初は難しく感じるかもしれないけど、経験を積めば自然と慣れるから大丈夫。わからないことがあったらすぐ聞いてね。

ありがとうございます、アキさん!これからはしっかり基準書やソフトのマニュアルを確認しながら進めてみます。

そうね、基準を理解して設計に活かす力が構造設計者としての成長につながるわ。これからの設計、頑張ってね!
【参考資料】
今回の記事では以下の情報を基に解説しました。実務に活かすためには、それぞれの資料を確認して詳細を把握してください。
- 建築基準法施行令
- 荷重設定の基準値が記載されています(特に別表第一)。
- 入手方法: e-Gov法令検索 で無料で閲覧可能。
- 建築構造設計基準(日本建築学会)
- 各荷重の詳細や組み合わせ方法について解説。
- 構造計算指針(日本建築学会)
- 地震荷重や風荷重などの具体的な計算手順が記載。
- 一貫計算ソフトのマニュアル(例: BUS-6、SS7など)
- 荷重設定や組み合わせ条件の操作手順を確認できます。
- 県・市のホームページ
- 市の条例等で別途に条件を定めている場合があるので注意が必要です。
まとめ
荷重の設定は、構造計算書を作成する上で非常に重要なプロセスです。この記事では、建物にかかる力を「固定荷重」「積載荷重」「積雪荷重」「風荷重」「地震力」の5つに分類し、それぞれの特徴や考え方を解説しました。また、設計においては荷重を適切に組み合わせることが欠かせません。長期荷重や短期荷重を正しく設定し、安全性を確保するため、一貫計算ソフトの設定値を確認・調整することがポイントです。
さらに、建築基準法や日本建築学会の指針、自治体の基準などを参考にすることが重要です。用途や地域ごとの条件をしっかり確認し、必要に応じて他部署と連携しながら進めることが、実務では欠かせません。
建物の安全性を左右する荷重設定。この記事を通じて基本を押さえ、実務に役立ててください。初心者の皆さんが一歩ずつ成長していけることを応援しています!